フェルマーの小定理は、今日では初等数論の基本結果として知られている。しかし、この定理が「証明された理論」として定着するまでには、大きな思考の転換が必要だった。その転換点を担ったのが、レオンハルト・オイラーである。
ここでは、オイラーが1736年に執筆し、1741年に刊行された論文 Theorematum quorundam ad numeros primos spectantium demonstratio(Eneström E54)をもとに、 彼がこの論文で何を発見し、どのような気づきを得ていたのかを整理する。
1.フェルマーへの敬意と、はっきりした違和感
論文の冒頭でオイラーは、フェルマーが数論にもたらした多くの定理を高く評価している。一方で、はっきりとした問題意識も示す。
それは、フェルマーの多くの主張が 帰納法や経験的確認に強く依存している という点である。
オイラーにとって、
- 多くの例で成り立つ
- 計算上は疑いようがない
ということと、
- なぜ必ず成り立つのかを説明できる
ということは別問題だった。 ここでオイラーは、フェルマーの小定理を「既知の事実」ではなく、証明を与えるべき理論的課題として位置づけ直している。
2.「2の問題」ではなく「構造の問題」だという発見
オイラーはまず、フェルマーの小定理を
$$2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$
という形で扱う。 一見すると、これは「底が2の特殊な性質」のように見える。
しかしオイラーが注目したのは、数値そのものではない。
彼は
$$(1+1)^p$$
という二項展開を用い、中間項のすべてが $p$ を因数にもつという事実に着目する。
ここで得られた重要な気づきは次の点である。
この定理が成り立つ理由は、 2という数にあるのではなく、 素数 $p$ と二項展開の構造そのものにある
つまり、フェルマーの小定理は偶然の計算結果ではなく、代数的構造から必然的に生じる性質だと見抜いたのである。
3.「これは一般化できる」という確信
論文の中盤で、オイラーは次の一歩を踏み出す。
この性質は、2に限られないのではないか?
ここで彼は、
$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (p \nmid a)$$
という一般形を明確に意識し始める。
この段階で、フェルマーの小定理は
- 特定の数の性質
ではなく、
- 素数に関する一般法則
として再定義されることになる。
この視点の転換こそが、オイラーの最大の「気づき」である。
4.別の形での定式化――「$a^p \equiv a$」
論文の後半でオイラーは、定理を次の形で書き換える。
$$a^p \equiv a \pmod{p}$$
現代ではよく知られたこの表現は、当時としては新鮮だった。
ここでオイラーが示しているのは、
- 「$p-1$乗」という形そのものが本質なのではなく
- 冪乗と合同の関係全体が重要だ
という理解である。
この見方は、後に「オイラーの定理」や、より一般的な数論的構造へとつながっていく。
5.この論文でオイラーが到達した地点
E54論文において、オイラーが得た成果は単なる「証明」ではない。 そこには、次のような段階的な気づきがある。
- フェルマーの主張は、証明されるべき理論的問題である
- 小定理の根拠は、計算ではなく構造にある
- この定理は一般化可能であり、数論の基礎原理になりうる
こうしてフェルマーの小定理は、 個人の直観的発見から、 共有可能な数学理論へと引き上げられた。
おわりに――フェルマーからオイラーへ
フェルマーは「結果を示した」。 オイラーは「なぜそれが成り立つのかを説明した」。
この違いは、単なる時代差ではない。 数学が「発見の集積」から「理論の構築」へと移行していく、その決定的な一場面が、この論文には刻まれている。
オイラーの1736年論文は、フェルマーの小定理を完成させただけでなく、数論そのものの姿勢を変えた論文だったと言えるだろう。
参考史料
Leonhard Euler, Theorematum quorundam ad numeros primos spectantium demonstratio (1736/1741), Eneström E54



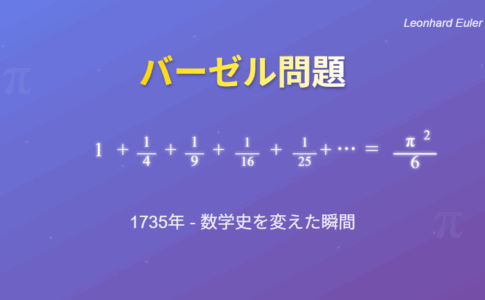
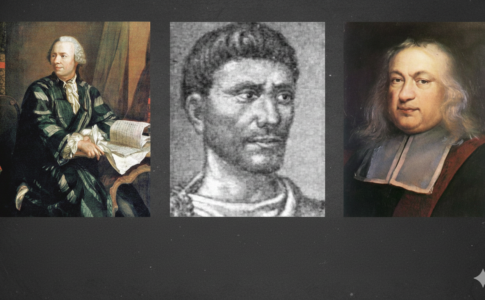
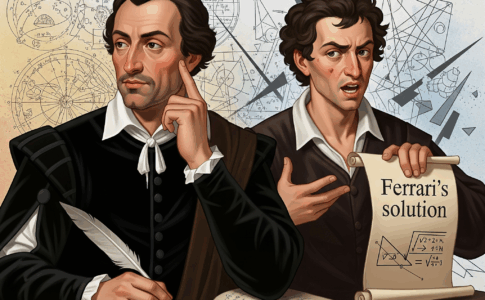



コメントを残す